そうそう、先日の話なのですが・・・
相も変わらずスタジオなどでの仕事を探し回っている日々で、何だか煮詰まりつつあったのですが、「もしかしたら自分に合った活動方法じゃないんじゃないか?」なんて事まで考え始め、ふと「そうだ、もっとオープンに宣伝活動をしてみたらどうだろう」と思い立ちました。
とは言っても、写真展を開くような予算は無いし・・・
なんてカフェで考えている時に、よく居酒屋でもレジ横等に置いてある名刺サイズのお店情報カードに気付きました。
皆さんはどうかわかりませんが、自分は結構お店のカードやチラシを持ち帰るクセがあるので、「いい!自分も宣伝用カードを作ろう!」と思い立って、早速家に帰ってカフェ等に置いてもらえるような写真を探す事にしました。
「カフェに立ち寄る人は、心のゆとりを求めて来る人が多い気がする」
「心のゆとりを求めている人なら、写真なんかにも興味を示してくれるような気がする」
みたいな勝手な思いも抱きつつ・・・
帰る途中に、カードに載せる文字情報はどんなものがいいかを考え、簡潔に以下の三つに決めました。
・名前
・URL
・ご自由にお持ち下さい
それから家に着いて、配布許可の必要の無い、風景と花火の写真をいくつか探し出して、後はどんな用紙にプリントするかを考えました。
【用紙サイズ】
・名刺サイズだと小さすぎて、フォトグラファーの作品として認識してもらいにくい(気がする)
・A4サイズくらい大きいと、インパクトはあるけどお店側には邪魔だろうし持ち帰りにくいし(気がする)
などなど、大きさについて考えているうちに
「せっかくだから、持って帰るだけじゃなくて飾ってもらいたい」
という欲も出て、
それならばと、ポストカードサイズに決めました。
このサイズなら、まぁお店にもよると思いますが、ギリギリ置いてもらえるかなぁ・・・なんて。
紙の種類は、最近プリントしたときの素朴な仕上がりが気に入っている画用紙に。
そして家に帰って、数種類、合計数十枚のポストカードが完成。
まずは、以前働いていた会社の近くの神谷町オープンテラスに連絡し、置いてもらいました!
出来るだけ多くの人に持っていってもらえると嬉しいです。
皆様も、是非近くにお寄りの際は一枚と言わず五枚でも十枚でも(ちょっとしか置いてないけど)。
快く置いて下さった店長、ありがとうございます<(_ _)>
そして、更にもう一店、カードを置いて下さるお店が見つかりました!
実際にカードを置いてもらった時に報告したいと思います。
今日その資源を利用せずに日常生活を送ることは難しく、地球への負担は避けられない問題となっております。
しかし限りある資源をきちんとリサイクルしてゆくことで、その負担は軽減する事が出来ます。
そして消費者として出来る事は、賢くそのリサイクル商品を使っていくこと。
私は宣言します。
地球に優しいフォトグラファーになります!
というわけで、自宅でプリントする機会の多い私は、
手始めに、『リサイクルインクカートリッジ』の利用を積極的に行っているわけです。
↓
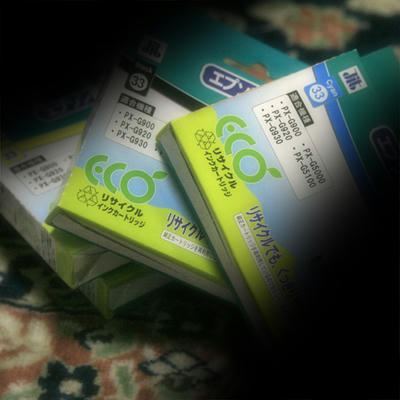
EPSON純正のインクとはやっぱり多少色合いが違ってくるのですが、
インクのせいで「変」になる事は滅多にありません。
それよりも、撮影時の設定、編集時、用紙の質によっての方が、色合いに大きく違いが出てきますよね。
それに、純正品より値段が安い事も利用者にとってはメリットでしょう。
数百円違うんですよ(^^;;
と、前置きが長くなりましたが、今日はそのインクを買いに久々にヨドバシに行ってきたわけです。
電車賃はたいて・・・。
今日は
シアン
マゼンタ
イエロー
フォトブラック
マットブラック
の五色を買いました。
一色800円で、合計4000円。
・・・まあ、安く買えるとはいえ、清貧フォトグラファーとしては高価に違いないんですけどね。
他にヨドバシで買ったのは、
キヤノン
エコノミーフォトペーパーお特用400枚入り大増量パック
2000円
あと世界堂にて、
マルマン
Mi-Teintes(ポストカードサイズ・紙厚160g/㎡・100枚)
800円
↑これはエンボス加工の施された画用紙(『世界No.1シェアを誇る”大人の色画用紙”』だそうです。)
そして、ヨドバシを出たら大雨になっていたので、慌てて買ったビニール傘150円。
なんか、インク以外は全然ECOじゃないなぁ。
追伸
カメラとの生活 プライスレス

http://cola.chitosedori.com/sub_Work/Work_00.htm
「福田流花火撮影法」は、花火写真家の福田武さんが考案した、花火の特殊な撮影方法です。
←一見、普段目にする花火とは全く違うもののように見えますね。
とある写真雑誌記事でその存在を知り、記事の通りやってみようという事で東京湾の花火大会に行ってきた時の写真です。
実際に撮ってみると、花火大会の花火って打ちあがる場所も毎回微妙にズレるし、上がって花が開く高さも、みんな違うんですね。
三脚にカメラを固定して、花火を追いかけながら撮るわけですが、花が開くポイントを見定め、そこできっちりカメラを固定しないといけないわけで、それがとても難しかった。
上がる場所が大体読めてきたら、そこに固定してジッと待つ・・・。
しかし慣れるまで待つ時間がもったいないように感じ、結局全部にシャッターを切り、そして大半が微妙に手ブレていたのでした('A`)
掲載している写真は、外枠部分にノイズをかけたり薄くしたりとPhotoshopで加工してます。
掛け軸で言うと中回し(?)的な役割を果たす部分とでもいいましょうかね。
そんなわけで、和な風情のあるものがあったり、ちょっと面白いかもしれません。
(「始めたばかりのクセに勝手にアレンジするな」と言われそうですが)
当たり前ですが、ちゃんとした福田流花火撮影法は、福田さんの公式サイトをご覧ください<(_ _)>



